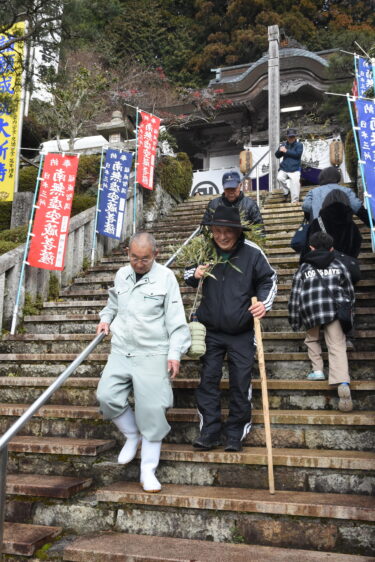人形峠の一帯が、1955年のウラン鉱床発見を機に、鉱山や研究施設に様変わりしていく中、地元の旧上斎原村もまちの表情を変えていった。
「明るい話題。住民の間で盛り上がったのを覚えている」
近くの赤和瀬地区で生まれ育った吉川元春さん(92)が、鉱床発見の報が届いた時の様子を振り返った。家業の炭焼きを手伝っていたが、原燃人形峠出張所が設置されると、近隣の人の誘いもあって就職。製錬工場などの技師として、89年に定年退職するまで約30年間勤めた。
村史などによると、森林が豊富なため、吉川さんのように木炭で生計を立てる家は多かった。村内で年間約900㌧を生産していた時代もあるが、戦後は近代化の中で衰退の兆しを見せていた。ウラン発見はそんな矢先の出来事だった。
採掘が始まると原燃は雇用を増やし、60年には、村の人口が、発見当時より約120人増えて約1740人に達した。だが、全国の中山間地域と同様、都会への流出の波に逆らえず、75年には約1120人に減っている。
「上斎原には、ウランしか残されていないんだ」。村議でもあった吉川さんは、当時の三船続昌村長がしきりにそう話していたのを思い出す。過疎にあえいでいたその頃、国がウランを濃縮する遠心分離機の試験工場の設置を計画。村内の意向はすぐにまとまり、国と動燃に建設を陳情した。早くも77年には起工式に至っている。
誘致の成功は、静かな農村の〝ウラン景気〟の始まりだった。
原発関連施設の立地地域が対象となるいわゆる「電源交付金」として、建設時に約21億円の巨資を手に。当時の一般会計予算よりも優に多く、半分がつぎ込まれた幼稚園・小中学校の総合教育施設「上斎原学園」は村の近代化のシンボルとなった。その後も別の関連交付金をもらい続け、道路拡幅や上斎原文化センターといった公共施設の建設、恩原高原スキー場や国民宿舎いつきなどの整備に生かされている。
一方、濃縮試験工場完成の同時期、すぐそばに「人形峠原子力産業株式会社」が誕生した。村が出資し、社長は三船村長。施設の警備や清掃、食堂運営などの雑務を一手に引き受けた。これが地元の雇用を生み、Uターンも促した。84年9月の津山朝日新聞の連載「ウラン景気の上斎原村」によると、当時の社員134人のうちの30人が長男のUターン組。動燃人形峠事業所にも約450人の従業員がおり、近くに商店も並んで地域経済は潤ったという。
村役場で振興計画などを担当した牧野康平さん(66)は「人形峠は地域の維持、発展に欠かせない存在で、互いに良い関係を築いた。ウランが無ければ過疎はさらに深刻だったはずだ」と語る。
村としての生きる道は確かに定まっていた。しかし、致命的な〝誤算〟があった。
濃縮ウランを製造する「商業プラント(工場)」の誘致の失敗だった。技術の開発、実証を担う「原型プラント」がそれまでに建てられており、シナリオはできていた。地元の反対も無く好条件と思われたが、2000年、青森県六ケ所村での体制の一元化が決定。人形峠は事業縮小を余儀なくされた。
上斎原のまちは再び、過疎対策や雇用の確保などの命題を突き付けられたのだった。
P①
旧上斎原村が国道沿いに建てた看板。人形峠が地域にとって大切な存在だったことを感じさせる

村が出資して設立した人形峠原子力産業株式会社。地域の雇用を生んでいる

電源交付金で建てられた総合教育施設「上斎原学園」(少子化により2020年4月から全面休校)